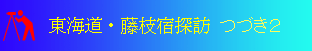
 |
「旧東海道と御成街道」
旧東海道の岡部宿を通り葉梨川に架かる八幡橋の突き当たりを右 (西南方向)に向かって進むと藤枝宿に至り、左(東南方向)に向かって 進む道が御成(おなり)街道であって、1.7kmほどで田中城の平島木戸 に通じる。家康は、駿府城に隠居していたとき鷹狩によく出かけ、 その折この街道を通って田中城を訪れたといわれている。 御成街道は、田中城への登城口として、戦国時代には武田信玄、 織田信長、家康などの武将が通った歴史ある古道だ。 |
|
「馬上の清水」
家康がこの地で鷹狩をしたとき、喉が渇いたので家来に汲ませて、 馬に乗ったまま水を飲んだので、この名がついたといわれている。 |
 |
 |
「芝原延命六地蔵尊」
天王町・市部第二町内にあるこの地蔵尊は、1707年(宝永4年) 10月の宝永大地震、11月の富士山大噴火の翌年、市部村民が、 天災から免れるように、また恐怖からの救済を願って造られたと言う。 今年(平成20年)は地蔵尊開眼300年にあたり、地元では、 8月24日に300年祭を開き祭事が行われた。記念誌もつくられている。 江戸時代、この地区は、旧東海道に面した家は、白子宿、下伝馬宿 の所属となり、そのほかは市部村に所属したようだ。(記念誌参照) (関連写真4枚掲載) |
|
「百万遍」
お地蔵さんの前で、1、080顆ある大数珠を、「南無阿弥陀仏」 と唱えながら回す行事。 「百万遍」の目的はいろいろあるようだが、市部の場合は、 享保の大飢饉の年から始まったようなので、五穀豊穣の願い が目的であったといわれている。 |
 |
 |
「百万遍」
老若男女が大勢集まり、願いをこめて回す。 |
|
「お地蔵さん」 300年の長きにわたり、衆生の願いを聞き、導いてきた 尊いお地蔵さん六像のうち、金剛幢地蔵(こんごうとうじぞう) を撮影できたので、失礼と思うが掲載した。 修羅の世界から救ってくれるお地蔵さんだ。 (台座を含めた高さ69㎝、石造) (詳細は記念誌参照) |
 |

